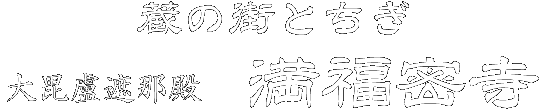「男色」ということ
令和5年10月01日
寺院の住職のブログに「男色」などという性タブーを書くのもいささか場ちがいな気もしますが、昨今思うところあり、敢えてふれてみる次第です。
長く女人禁制だったお寺には、実は昔から男同士の性行為「男色」がありました。京都の大きな禅寺で九才から童子・沙弥を経験した作家水上勉氏は、自著『一休』で禅寺における「男色」の実際を赤裸々に書いています。その内容はとてもここに紹介できるものではありませんが、多くは師僧(禅寺では、老師・師家という)が自分の弟子や近侍の沙弥・童子(十才台の年令)を相手に行ったもので、最近の某芸能プロ経営者の例に酷似した性加害、セクハラです。
おそらく老師の夜伽の相手を拒めば、弟子や沙弥や童子に労役加増などのいじめや僧堂生活上の差別その他の人権侵害が待っていたのでしょう。老師の夜伽に付き合うことは十才台の少年にとって苦痛以外の何ものでもなかったにちがいありませんが、禅寺に入門を許された以上とくに老師には絶対服従です。しかし、禅寺の「男色」は老師と弟子や近侍の沙弥・童子ばかりでなく、兄弟子と弟弟子、入門の先輩と後輩、年上と年下の関係でもあったことは想像に難くありません。さすがに今はもう無いと思いますが、水上勉氏の十才台まで当然の如く行われていました。
長く女人禁制だったお寺には、実は昔から男同士の性行為「男色」がありました。京都の大きな禅寺で九才から童子・沙弥を経験した作家水上勉氏は、自著『一休』で禅寺における「男色」の実際を赤裸々に書いています。その内容はとてもここに紹介できるものではありませんが、多くは師僧(禅寺では、老師・師家という)が自分の弟子や近侍の沙弥・童子(十才台の年令)を相手に行ったもので、最近の某芸能プロ経営者の例に酷似した性加害、セクハラです。
おそらく老師の夜伽の相手を拒めば、弟子や沙弥や童子に労役加増などのいじめや僧堂生活上の差別その他の人権侵害が待っていたのでしょう。老師の夜伽に付き合うことは十才台の少年にとって苦痛以外の何ものでもなかったにちがいありませんが、禅寺に入門を許された以上とくに老師には絶対服従です。しかし、禅寺の「男色」は老師と弟子や近侍の沙弥・童子ばかりでなく、兄弟子と弟弟子、入門の先輩と後輩、年上と年下の関係でもあったことは想像に難くありません。さすがに今はもう無いと思いますが、水上勉氏の十才台まで当然の如く行われていました。
「男色」。これをウェブで検索しますと、単純に「同性愛(ホモ・ゲイ)」だという説明が目立ちますが、私がここに言う「男色」は、本能的に女性には性的関心も性欲もわかない男同士が日常的に性愛を交わし同棲や同性婚を是とするいわゆる「同性愛(ホモ・ゲイ)」とは異なり、女性のいない男だけの閉鎖世界でやむなく男同士で性欲を発散する性行為のことです。
出版物などによれば、「男色」のはじまりは、井原西鶴の『男色大鏡』にある古代の神話や『日本書紀』に言う「阿豆那比(あづなひ)の罪」の物語は別として、平安期の『伊勢物語』『源氏物語』からすでに宮中・貴族の間で見られ、藤原頼道・道長親子の男色が『教訓抄』『台記』に書かれ、武家政治の時代になると足利義満・足利義政の二将軍、戦国時代の主君と小姓の「衆道」、武田信玄・織田信長・徳川家康・伊達政宗など、江戸時代には松尾芭蕉が「寒けれど二人寝る夜ぞ頼もしき」「草の枕のつれづれ二人語り慰みて」(『笈の小文』)と意味深な句を残しているほか、歌舞伎の世界においては「若衆」歌舞伎の「男色」文化が盛んになり、幕末には新撰組にもあり(近藤勇の書簡)、明治になって森鴎外の『ヰタ・セクスアリス』・坪内逍遥の『当世学生気質』には学生寮・学生間での「男色」が書かれ、里見弴・芥川龍之介・菊池寛・武者小路実篤・堀辰雄・太宰治・川端康成などには大なり小なりその気配があったと言われています。
専門家によれば、歌舞伎の世界では「男色」が独自に展開し、歌舞伎役者のなかには「昼は舞台、夜は男色」があったとも言われています。歌舞伎役者には「男色」を容認する特殊な芸的背景があったのかもしれませんが、歌舞伎の世界には世間的にはタブーであることを芸に役立てて容認する「秘めごと」があったのかもしれません。女形(おやま)を演じる役者が日常生活でも女性的な事例はいくつもあり、夜「男色」の相手になることはあり得ることでしょう。また、男ばかりの軍隊では日露戦争の頃から「男色」があってしばしば性病まん延のもとになり、性病の患者が多くいる部隊は戦闘行為に支障をきたすことから、大東亜戦争下においては国外に駐屯する部隊に健全な従軍慰安婦が用意されました。しかし慰安婦も用意されない潜水艦のなかでは「男色」は避けられず、これも戦時体制という非常時の公然の「秘めごと」でした。
出版物などによれば、「男色」のはじまりは、井原西鶴の『男色大鏡』にある古代の神話や『日本書紀』に言う「阿豆那比(あづなひ)の罪」の物語は別として、平安期の『伊勢物語』『源氏物語』からすでに宮中・貴族の間で見られ、藤原頼道・道長親子の男色が『教訓抄』『台記』に書かれ、武家政治の時代になると足利義満・足利義政の二将軍、戦国時代の主君と小姓の「衆道」、武田信玄・織田信長・徳川家康・伊達政宗など、江戸時代には松尾芭蕉が「寒けれど二人寝る夜ぞ頼もしき」「草の枕のつれづれ二人語り慰みて」(『笈の小文』)と意味深な句を残しているほか、歌舞伎の世界においては「若衆」歌舞伎の「男色」文化が盛んになり、幕末には新撰組にもあり(近藤勇の書簡)、明治になって森鴎外の『ヰタ・セクスアリス』・坪内逍遥の『当世学生気質』には学生寮・学生間での「男色」が書かれ、里見弴・芥川龍之介・菊池寛・武者小路実篤・堀辰雄・太宰治・川端康成などには大なり小なりその気配があったと言われています。
専門家によれば、歌舞伎の世界では「男色」が独自に展開し、歌舞伎役者のなかには「昼は舞台、夜は男色」があったとも言われています。歌舞伎役者には「男色」を容認する特殊な芸的背景があったのかもしれませんが、歌舞伎の世界には世間的にはタブーであることを芸に役立てて容認する「秘めごと」があったのかもしれません。女形(おやま)を演じる役者が日常生活でも女性的な事例はいくつもあり、夜「男色」の相手になることはあり得ることでしょう。また、男ばかりの軍隊では日露戦争の頃から「男色」があってしばしば性病まん延のもとになり、性病の患者が多くいる部隊は戦闘行為に支障をきたすことから、大東亜戦争下においては国外に駐屯する部隊に健全な従軍慰安婦が用意されました。しかし慰安婦も用意されない潜水艦のなかでは「男色」は避けられず、これも戦時体制という非常時の公然の「秘めごと」でした。
ここに私が言う「男色」は、男同士のかっこよくない「秘めごと」であり、白昼には口にしない夜の「秘めごと」であり、当事者だけの「秘めごと」であり、表だって口にするものではありません。だから、井原西鶴も森鴎外や坪内逍遥も文学的表現という仮構にして世に出しました。仮構の世界なら、世間的にはアブノーマルなことを逆に楽しんで自分のなかでノーマル化する(不道徳の)美学も可能ですし、アンダーグラウンド的な美意識の表出も可能です。
このたびの某芸能プロ経営者による性加害の闇は、男同士の「秘めごと」レベルの「男色」にとどまらず、彼の「男色」が街角からお気に入りの美少年を見つけ出し、彼の「男色」の対象になったその美少年たちが彼の「男色」をエンターテイメントで体現し、それを通じて彼の「男色」は事業化(社会化)され、その結果事業の維持・発展にとって彼の「男色」はますます欠かせないものになったということです。すなわち、彼にとって若年アイドルへの性行為の強制は、自分の事業の維持・発展の源泉と化したのです。従って、事業の維持・発展のためには、「男色」の相手がたとえ十才台の未成年者であっても、その将来や人権など無視されたに相違ありません。これが某芸能プロ経営者による性加害事件の闇で、ここが問われなければならないでしょう。ひるがえって、今日本でよく報道される性暴力(セクハラ)の問題も、結果論としての人権侵害・人権救済・損害賠償や加害者の責任問題に目を向けるばかりではなく、問題の根源にある人間の性欲(本能)とその自制(理性)のあり方が問われなければ、いつまでも終りが見えないでしょう。
このたびの某芸能プロ経営者による性加害の闇は、男同士の「秘めごと」レベルの「男色」にとどまらず、彼の「男色」が街角からお気に入りの美少年を見つけ出し、彼の「男色」の対象になったその美少年たちが彼の「男色」をエンターテイメントで体現し、それを通じて彼の「男色」は事業化(社会化)され、その結果事業の維持・発展にとって彼の「男色」はますます欠かせないものになったということです。すなわち、彼にとって若年アイドルへの性行為の強制は、自分の事業の維持・発展の源泉と化したのです。従って、事業の維持・発展のためには、「男色」の相手がたとえ十才台の未成年者であっても、その将来や人権など無視されたに相違ありません。これが某芸能プロ経営者による性加害事件の闇で、ここが問われなければならないでしょう。ひるがえって、今日本でよく報道される性暴力(セクハラ)の問題も、結果論としての人権侵害・人権救済・損害賠償や加害者の責任問題に目を向けるばかりではなく、問題の根源にある人間の性欲(本能)とその自制(理性)のあり方が問われなければ、いつまでも終りが見えないでしょう。
その上で、敢えて駄弁を弄しますが、歌もダンスも下手くそな美少年を複数集めてアイドルグループにし、一人一人の歌・ダンスの下手さを美少年特有の未成熟な色気(セクシャリティ)でごまかし、母性や「男色」をくすぐる偽計商法。これを誰かがマネし、歌もダンスも下手な美少女を何人も集めてアイドルグループにし、やることと言えば、歌やダンスの下手さを超ミニ・下半身丸見えのエロチシズムでごまかし、男の性欲と女の母性をくすぐる偽計商法。もとはと言えば、例の某芸能プロ経営者の「男色」がはじめた未成年アイドルを使うセクシャル商法。この少年・少女を商売のオモテ道具とし、そのウラで大人がほくそえんでいる悪業。時代劇のセリフではありませんが「お前も、悪よのう」です。この機会に、少年・少女を商売の道具に使う、先進国にあるべからざる悪徳商法も、厳しく問われて然るべきです。
戦後間もない頃から東京の銀座七丁目に「銀巴里」というシャンソン喫茶があり、美男の歌手が人気を博していました。みごとな声量、たくみなフランス語で、シャンソンの名曲をライブで歌っていました。丸山明宏、今の美輪明宏です。彼はのちに、ユニセックスファッションを着た美男として「シスターボーイ」と言われましたが、「銀巴里」にはフランス志向の画家やデザイナーや作家や文学者や思想家がよく来て、丸山明宏の「メケメケ」「ラ・メール」「パリの空の下」「さくらんぼの実る頃」などを聴いていましたし、彼のユニセックスは当代一流の文化人から支持されていました。作家の三島由紀夫・野坂昭如・吉行淳之介・遠藤周作、服飾デザイナーの中原淳一、劇作家の寺山修司、作詞家のなかにし礼などは常連でした。彼は同性愛であることをのちに公けにしましたが、その性的嗜好・思考はフランス文化の影響を受けていて、シャンソンのほかにも絵画や演劇や音楽や文学や思想等を通じてフランス文化の体現者のようでした。当時はフランスの実存主義(サルトルなど)が日本でもいろいろな分野・階層を動かしている時代でした。彼のユニセックスはそうした時代のフランス文化のなかに置くことができますが、例の某芸能プロ経営者の「男色」には子供だましのような商魂はあっても、洗練された大人文化の香りがありません。