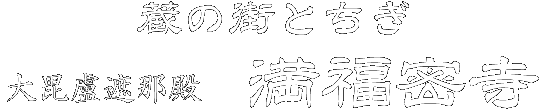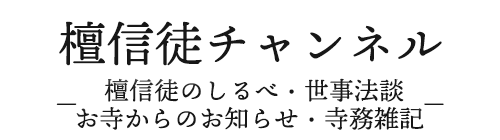
寺務雑記
■2025年07月01日(火)
「大師堂」の前にある「掲示板」を更新しました。今月は、お盆・夏の俳句です。
次世代を担う若い人たちに、俳句・和歌など日本語のふくよかな短文文化をお勧めします。心と頭の「糖尿病」といわれる「SNS短文依存症」の良薬です。
メール・ラインのやりとりも俳句や和歌でやったらどうでしょう。殺風景で軽薄短小なコトバでなく、ふくよかで美しい日本語の短文がネット上にも飛び交うことを願っています。
暑き日を 海にいれたり 最上川 ※玉祭:魂祭=お盆の供養。 亡くなった妾の寿貞尼を想って芭蕉が「とるにたらない身だなどと思ってはいけない、ちゃんとお盆の供養をするから」と詠んだ句。 ※蓮池や:池に咲く蓮の花を、折らず(切らず)にそのままにしておくのも、お盆の供養にはいいではないか、といった句。 | 松尾芭蕉 |
| 魂祭 盆の月 ※鉦の音:お盆にわが家へ帰るご先祖を迎える、お寺で鳴らす鉦の音 | 正岡子規 |
迎え火を おもしろがりし 子供哉 夕立ちや かゆき所へ 手のとどく | 小林一茶 |
| 送り火や 母が心に 風が吹く 仏来給ふ けはひあり | 高浜虚子 |
涼しさや 鐘をはなるる かねの声 ※地蔵会:京都の地蔵盆。 ※銀閣:銀閣寺。五山の送り火の第一、如意ヶ岳の「大」文字の下でにぎわう。 ※浪華:波の花。波の花が浜辺に集るように、銀閣寺の周辺に送り火とともに先祖を見送る人がおおぜい集っている。 | 与謝蕪村 |
| トマトを掌に みほとけのまえに ちちははのまえに 水は岩から お盆のそうめん 冷やしてある いなびかり 別れて遠い人をおもふ | 種田山頭火 |
| 紫の キキョウ ミソハギ 墓に伸び 雑草の故 刈り取られ 新盆を 迎える友の 多かりき | 住職 |